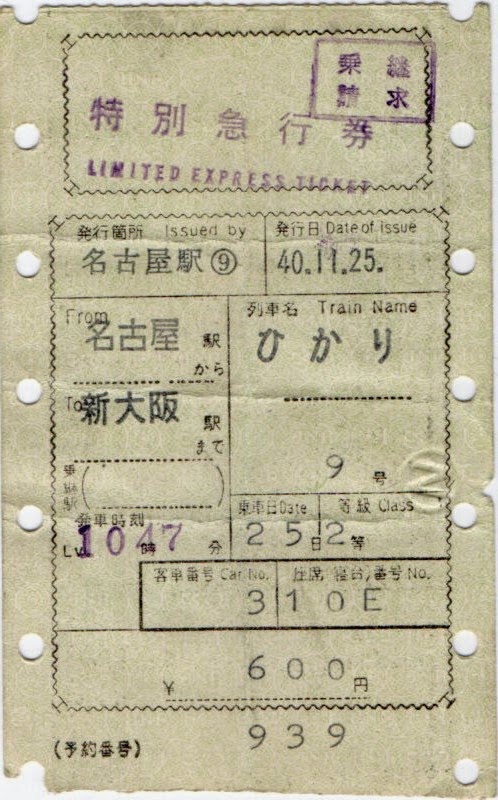皆様こんばんは、専修大学鉄道研究会です。
山陰・北陸・北海道と三手に分かれる夏合宿は、先月下旬の山陰組に続いて、北陸組が昨日全日程を終了し、現在は北海道組が現地に滞在中という状況です。いずれも後日報告が何かしらの形であると思いますのでお楽しみに。
今回は「会長の近況」第3弾をお送りします。
第1弾において、8月20日(水)に東海道線で名古屋に行った、というお話をいたしました。
その際の名古屋滞在時間は2時間余りでした。その中で色々やり残したことがあるように思えたので、もう1回、今度は名古屋近郊を目指して行きました。
そのやり残したこととは、東海道線の笠寺駅と稲沢駅に行くこと、もう1つはJR東海のキハ40系に少しでも乗車することでした。笠寺駅と稲沢駅に行くのは貨車や機関車を見るため、キハ40系に乗るのは、同社のキハ40系の後継車両となるキハ25系1000番台がいよいよ落成したことによるものでした。
実行日は9月5日(金曜日)です。実家最寄駅から、始発の普通列車中津川行きに乗って行動を開始しました。以下の写真は、例によって、特記の無い限り、その日に私が撮影したものです。
中津川まではJR東日本の211系に乗りました。中央西線は現在JR東海の管轄ですが、1日2往復、長野総合車両センターの211系が普通列車として乗り入れます。始発の中津川行きはそのうちの1本に当たります。
中津川からは快速名古屋行きに乗り換えます。乗車した列車はかつて「セントラルライナー」として使用されていた313系8000番台の充当でした。
以前は名古屋~多治見間で別料金を徴収していた列車に使用されていただけあって、他の313系と比べ塗色や内装が異なっているのが特徴です。
数ある313系のバリエーションの中でも最も上級に位置するであろう「セントラルライナー」用に製造された8000番台の様子。
中津川駅にて
名古屋駅に着いた後、ホームを歩いていると、2編成しかないJR東海の211系0番台を見ることが出来ました。
JR東海の211系0番台は4両編成が2本だけ、しかも朝夕に、関西線でしか乗れないらしい。
今やJR東海で現役の電車の中で一番古いものになった。
名古屋駅にて
その後、前回と同様立ちきしめんを食べました。ただし、違う店で…
名古屋からは東海道本線で少し東の方向へ向かい、笠寺駅に行きました。笠寺に着くと、ちょうど前回も名古屋駅で見かけた石灰石を運ぶ貨物列車が到着していました。
かつて青梅・南武線でも見ることの出来た石灰石のホッパ車「赤ホキ」であるが、現在は名古屋地区のみで現役である。
この辺りの「赤ホキ」は粒の細かい石灰石を運ぶことがあるようで、粒が飛散しないようにカバーを付けている車両があるのが特徴である。
とは言え、カバーの付いていない車両もいる。これが「赤ホキ」の本来の姿である。
「赤ホキ」はほとんどの車両が製造から45年を超えたため、現在世代交代が進んでいる。
これが新しい「赤ホキ」で、今までの車両と形はほとんど変わらないが、より速く走れるらしい。
「赤ホキ」が出発して行った後、隠れていたこんな貨車が姿を現した。
これは、2両1組で専用のコンテナを使って片道はその中に乗用車を入れて運び、もう片道は普通のコンテナを専用のコンテナの中に入れて運ぶ、という目的で作った低床構造の貨車である。最近はここにずっと留め置かれているという。
以上4枚すべて笠寺駅にて
笠寺駅を後にして、第2の目的である「キハ40系に乗る」を目指して岐阜駅を目指しました。
途中JR貨物の愛知機関区が見れる稲沢駅に立ち寄りました。色々な機関車が置かれていて見ていてなかなか面白かったです。
ホームから見える位置に国鉄色のDD51がいた。但しこれは休車になっているようだった。
DD51は更新色の物もいた。こちらの方は動いているらしい。
既に引退したEF64の0番台も残っていた。私の鉄道趣味のルーツの1つは、地元を走るEF64の0番台の貨物列車であった。
見ていると見覚えのある機番があって(当然か?)懐かしく思った。
以上3枚すべて稲沢駅にて
岐阜駅に着いて昼食を食べ、高山本線に入りました。その後の時間帯にちょうど普通列車の飛騨古川行きなるものがあったので、これならキハ40系に乗れるだろう、と思ってホームに上がると、キハ40とキハ48の2両編成の列車が停まっていました。
手前はキハ40系の片開きの扉の両運転台車であるキハ40、奥は片開きの扉の片運転台車であるキハ48になる。
奥のキハ48は、高山本線が台風で寸断された際に不通区間に閉じ込められたことのある車両であった。
岐阜駅にて
途中美濃太田で下車し、太多線で多治見に向かおうとしました。すると、キハ25系1000番台の試運転にたまたま遭遇しました。
現在武豊線で使用されている0番台と同様、313系に似ているキハ25系1000番台。
しかし、長らく付けられていた側面のビードが無くなったり、車内がロングシートになっていたりと細かい所で差異が見られる。
しばらく美濃太田駅に留まったのち、太多線の普通列車多治見行きで移動を再開しました。
キハ25の試運転が来る前に撮影した、キハ40系の両開きの扉の片運転台車であるキハ47。これがそのまま多治見行きになった。
以上2枚すべて美濃太田駅にて
多治見に着いた後はそのまま実家に戻らずに、211系の快速列車で一旦名古屋駅に戻った後、実家向けの土産を買った後、前回と同じ列車で帰宅しました。
「会長の近況」第3弾、いかがでしたでしょうか?
次はいつになるか未定ですが、次回もよろしくお願い致します。
~専修大学鉄道研究会からのお知らせ~
専修大学鉄道研究会では新規会員を募集しています。学年・学部・性別等は問いません。
必要なのは「鉄道旅行に出たい!」「鉄道写真を撮ってみたい!」「鉄道模型走らせたい!」「何でも良いから鉄道に関する話をしたい!」というあなたの気持ちです。
「鉄道関係あんまり詳しくないんだよなぁ・・・」と不安になっているあなたもご安心下さい。
当鉄道研究会には鉄道に関する知識の浅い・深いを問わず様々な会員が所属しています。
各会員で色々な情報交換をしながら楽しく活動していきましょう!